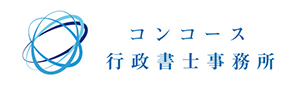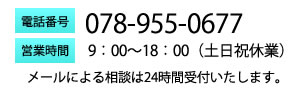最終更新日 2025年03月24日
古物商(古物営業)許可申請手続及び書類作成報酬のご案内
このページでは古物商(古物営業)許可の申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
- 古物商許可が必要な場合
- 古物商許可取得の要件
- 古物商許可申請の申請書記載事項
- 古物商許可申請書の様式及び記載例
- 古物商許可申請の際に必要な添付書類
- 古物商許可申請の窓口・提出先
- 古物商許可申請に係る申請手数料について
- 古物商許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
- 古物営業許可業者の遵守事項について
- 古物商許可取得後に行う必要な手続について
- 古物商許可更新手続について
- 古物営業許可の相続や合併等の承継手続について
- 古物商許可申請書作成や申請手続でお困りの時は?
- 古物営業許可申請手続代理に含まれる業務内容
- 古物商許可申請書の作成および提出代理の報酬について
- ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
- 古物営業許可を受けることができない、といわれたときは?
- 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
- 古物営業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
- 関連リンク
古物商許可が必要な場合
古物営業を営む場合は都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
以下のような営業を受ける場合は、許可申請が必要です。
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物 を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
- 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。)を経営する営業
- 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)→インターネットオークションなど
古物営業法の「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
一度使用された物品に含まれるもの
| 対象物 | 対象となる物品 |
|---|---|
| 鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物 |
|
一度使用した物品に含まれないもの
以下の物品は、古物営業法の対象外となります。
| 対象外物品 | 具体例 |
|---|---|
| 大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。) |
|
古物商許可取得の要件
古物商許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けることができるかどうかを最初に確認しておきましょう。
Ⅰ 古物商許可申請ができない方(欠格事由)
以下の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることはできません。
| 欠格事由 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 破産者で復権を得ないもの | 破産して復権されていない方は申請することができません。 |
| 2 | 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者 | 以下の方は、申請することができません。
|
| 3 | 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 | 古物営業法施行規則第1条に定める罪に当たる行為をした方が該当します。 |
| 4 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの |
左記の規定に該当する方は、申請することができません。 |
| 5 | 住居の定まらない方 | 住居・居所などが決まっていない方などが該当します。 |
| 6 | 古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 | 許可を取り消された者が法人である場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含みます。 |
| 7 | 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しない方 | 聴聞手続中に許可証を返納した方は、5年間申請することができません。(相当な理由がある場合を除く。) |
| 8 | 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める方 | 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方が該当します。 |
| 9 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | 古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合は除きます。 |
| 10 | 営業所又は営業所管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある方 | 左記の規定に該当する方は、申請することができません。 |
| 11 | 法人の役員が1~8に該当する場合 | 法人の役員で1~8の事由に該当する方が対象になります。 |
Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)
営業所に業務を適正に実施するための管理者を置かなければなりません。
Ⅲ モノに関する要件
物的要件は特に定められておりません。
Ⅳ 場所に関する要件
場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。
Ⅴ 施設に関する要件
法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。
物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。
Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)
財産的要件は特に設けられておりません。
Ⅶ その他の要件
その他の要件を特に定められておりません。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを有料で調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
古物営業許可申請の申請書記載事項
古物商の許可申請書には、以下の事項の記載します。
| 申請事項 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | 個人申請の場合は、氏名及び住所、法人申請の場合は名称及び所在地を記載します。 |
| 2 | 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地 | 営業所の名称と所在地を記載します。 |
| 3 | 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分 | 以下の区分を記載します。
|
| 4 | 営業所に置く管理者の氏名及び住所 | 営業所に配置する管理者の氏名及び住所を記載します。 |
| 5 | 古物営業法第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする場合、行商をしようとする者であるかどうかの別 | 行商を行うかどうかを記載します。 |
| 6 | 古物営業法第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨 | ウェブサイトなどを使用して古物営業を行う場合は、URL等を記載します。 |
| 7 | 役員の氏名及び住所 (法人の場合) | 法人の場合記載します。 |
古物商許可申請書の様式及び記載例
兵庫県に提出する申請書の様式は、以下のリンクよりダウンロードしてください。
| 申請書様式 | 雛形 | 記載例 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 古物商・古物市場主許可申請書 | PDFファイル | 準備中です。 |
| 2 | 誓約書(法人) | PDFファイル | 準備中です。 |
| 3 | 誓約書(個人) | PDFファイル | 準備中です。 |
| 4 | 誓約書(管理者) | PDFファイル | 準備中です。 |
古物営業許可申請の際に必要な添付書類
古物営業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
| 添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 定款 | 法人の場合、必要です。 事業目的に古物営業が記載されていることが必要です。 |
○ | × |
| 2 | 登記事項証明書 | ○ | × | |
| 3 | 最近5年間の略歴を記載した書面 |
|
○ | ○ |
| 4 | 住民票の写し |
|
○ | ○ |
| 5 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを証明する誓約書を添付します。 以下の方のものが必要です。
|
〇 | 〇 |
| 6 | 身分証明書 (市町村長発行のもの。) |
市町村長が発行する、破産又は後見登録されていないことを証明する書類です。以下の方のものが必要です。
|
○ | ○ |
| 7 | 古物市場ごとの規約 | 古物市場の営業を行う場合に添付します。 | △ | △ |
| 8 | 古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料 | 古物営業をウェブサイト等で行う場合、アカウントの使用権限資料が必要です。 | △ | △ |
古物営業許可申請書の提出先
兵庫県の場合、営業所を管轄する警察署の生活安全課(2課制の警察署は生活安全第1課)又は刑事生活安全課に提出します。書類は正本と副本各1通ずつ作成します。
警察署の一覧表は兵庫県警察のページをご覧下さい。
古物商許可申請にかかる申請手数料について
申請手数料は19,000円です。都道府県の収入証紙で支払います。
収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページ(外部リンク)をご覧ください。
古物営業許可申請の標準処理期間(申請から決定までにかかる日数)
古物商許可申請の標準処理期間は40日です。(なお、古物市場は50日)
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
古物営業許可業者の遵守事項について
古物営業許可取得後に行う必要な手続
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
Ⅰ 変更届
申請書の記載事項(商号・所在地・役員等)に変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。
Ⅱ 廃業届
以下の事由が発生した場合、免許証を返納する必要があります。
| 返納事由 | 返納義務者 | |
|---|---|---|
| 1 | 廃業したとき | 許可証の交付を受けた者 |
| 2 | 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき | |
| 3 | 許可が取り消されたとき | |
| 4 | 名義人が死亡した場合 | 同居の親族、法定代理人、管理者 |
| 5 | 法人が消滅したとき | 清算人、破産管財人、消滅した法人の役員 |
古物営業許可更新手続について
古物商の許可には期限がありませんので、更新の手続の必要はありません。
古物営業許可の相続や合併等の承継手続について
現在準備中です。しばらくお待ちください。
古物営業許可申請書作成や申請手続でお困りの時は?
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
古物営業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
| 業務内容 | お問合せフォーム |
|---|---|
| 古物営業許可申請 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
古物営業許可申請手続代理に含まれる業務内容
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
1 許認可の調査
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
2 必要書類の取得
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
3 申請書の作成
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
4 申請書の提出代理
申請書の提出をお客様に代わって行います。
5 補正対応
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
6 許可証の受領
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
古物営業許可申請書の作成及び提出代理の報酬について
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 |
報酬(税込) |
| 古物商新規申請書作成 | 66,000円~ |
| 変更届 | 33,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。
古物営業許可を受けることができない、といわれたときは?
古物営業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
古物営業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
古物営業許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)
ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
| 業務内容 | お問合せフォーム |
|---|---|
| 古物営業許可申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |